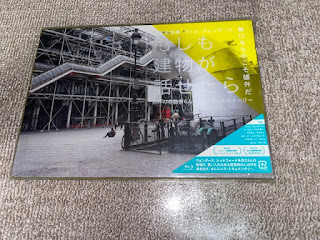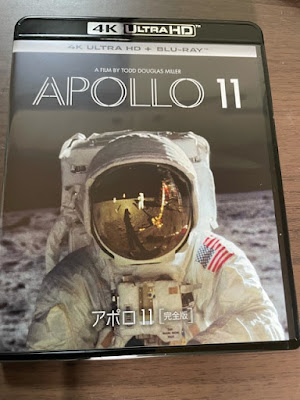ども、博多です。
「ホウレンソウ」についての話です。
社会人として仕事に就くと、常識となる「ホウレンソウ」ですが、よもや知らないなんて人はいないですよね?
いないですよね!(強調)
学生さんや就職されたことのない方もいらっしゃるかも知れませんので、補足しておきますと、
ホウ レン ソウ
ホウ ⋯ 報告
レン ⋯ 連絡
ソウ ⋯ 相談
の略語です。
業務する上で何か問題が発生した時に、素早く「報告」し、関係各位に「連絡」し、上司などに「相談」し、対処にあたるという、仕事を行う上での【基本中の基本】です。
これと絵コンテを切る事がどう関係するかというと、
・設定が足りてない
・コンテ打ちの際、確認するのを忘れた
・想定尺、想定カット数を大幅に超えそう
・スケジュール内に終わりそうにない
など、こちらの判断だけで解決しそうにない問題が起きることがあるからです。
まずひとつ目。
コンテ打ち後に設定を送ってもらう場合、制作さんがコンテ打ち中に出て来た必要な設定を聞き漏らしていたり、シナリオに明記されていないけど必要なものがあったりした時に起こります。
設定や参考などがないまま、フワッと描くとほぼ100%違います。(笑)
設定がない場合でも、監督とイメージを共有するために参考画像くらいはもらっておきましょう。
ニつ目。
これは確実に自分のミスなので、まずはちゃんと謝りましょう。
イメージの共有はコンテを切る上で最重要項目なので、どう描いて良いか分からない時は迷わず監督に確認しましょう。
三つ目。
慣れてくると作業前から薄々分かるようになりますが、シナリオを読んだ時には行けそうだと思っても、作業を進めていくうちに「どう考えても◯カットに収まる気がしない」とか、「セリフ多すぎて定尺に入れると早口喋りっぱなしになるんですけど!」となることがあります。
事前に連絡しておいて、監督に切りどころを決めてもらうか、大幅オーバーしたものを上げることを通告した方が良いでしょう。
監督もチェックに掛かる時間を予め想定しているはずなので、心構えができるはずです。
四つ目。
絵コンテのみ切っている場合は自分の管理ミスでしかありませんが、並行して演出処理などを行っている場合には突発的にイベントが発生(ゲームっぽい言い方だな)し数日作業が止まったりすることもあります。
余裕を持って作業していたとしても巻き返せないと感じたら、その時点で(ココ重要)制作に申告しましょう。
その際、少し余裕を持たせてアップ日を延ばしてもらいます。
これには二つ理由があります。
まずは「同じ状況がまた発生する可能性を考慮する」。
アップ日を延ばしてもらうということは、上がったコンテをもらう側、つまり制作のスケジュールもそれに合わせて修正されるということです。
以前も書きましたが、コンテが上がってから様々な部署のスケジュールが「一気に」動き出します。
なので、何度もアップ日を延ばしてもらうということは、それ以降の部署に同じだけ「リスケを強いる」ということですので、それだけは何としても避けましょう。
もう一つの理由としては、延ばしたアップ日より前に上げると「がんばって上げてくれた感が付与される」。
これは単なる心象であるし、制作さんもそれほど感じないと思いますが。一度延ばしちゃってるし。
コンテの遅れはそのまま、全体のスケジュールの遅れであることをしっかりと理解しておいてください。
余談……というかグチ。
コンテに限らず、予定アップ日スレスレまで作業が遅れている事を伏せている人をよく見かけますが正直、「意味が分かりません」。
伏せたところで状況は悪化一択ですし、心象もめちゃくちゃ悪いです。
「次から使うのやめよう」と制作さんに思われるし、他のスタッフからも「アイツのせいで……」と陰口叩かれまくりです。
「他人からどう思われようと知ったこっちゃねーよ!」的な図太さのない人は、悪い事は言いません、スケジュール落ちそうだなと思ったら、思った瞬間にすぐに報告してください。
制作ラインの中に数人いるだけでスケジュール崩壊しますんで、マジで。
……0点のテストを机に隠してる小学生じゃないんだから。
閑話休題。
てことで、「ホウレンソウ」は【基本中の基本】。
何かあったら、すぐに報告連絡相談しましょう。
では、また。
博多
リスケ ⋯ リスケジュールの略。スケジュール切り直し。